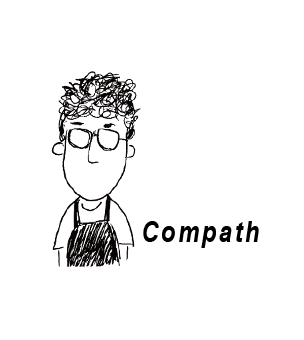2024/06/19 19:34
まず最初に、、この本文はnoteにて有料で公開しています。
あんまり大きな声で言いたくありませんが赤裸々な内容ですのでお菓子を見てくださっている方々には全文無料で紹介しています。
内緒ね。。
↓↓↓
僕はオンラインショップにてお菓子を、大阪平野のレストランにて料理を提供しているおっさんです。
基本的には数字が好きで、カヌレの作り方も失敗してきた過去もすべて数字でデータを取り、その分析から成功の道筋を考えるタイプの人間です。
どちらかといえば会計士的な数字を使ての感が和えをする僕ですが、オンラインでご紹介するお菓子やお店の料理などはまーーーったく原価計算をしていません。
それでいいとすら思っています。
ここでは【それでいい】と思える理由を赤裸々に書いていきます。
原価計算のたどりつけない領域
人の選択は電卓じゃない
まず、前提として僕は異本何も隠していません。
note等の記事で有料にしていることが【隠している】という反論をいただくことが多々ありますが、それは揚げ足取りです。
自分の経験してきた過去や、そこから得られた知見などは人それぞれ価値のものであると同時に、それに対価を払うのは当たり前のことで
僕は結構記事にお金を払ってほかの人の考え(頭の中)を拝見しているほうだと思っています。
ぼくは心の中で(原価計算にはたどり着けない領域がある)と思っています。
飲食店の現実を皆様の目のまえに披露したいと思いますが、実際売り上げの10%が手元に残ったら上出来で、それ以下で(普通)という評価です。
これは100万円の売り上げがあったら、個人事業主の場合は10万円の給料があったら良いほうという結果になります。
ここから先はある程度余裕がある(資産があったり、配偶者が別に収入がある)といった状況でしか語れないことかもしれませんが、
飲食店の値決めは1番最後です。基本的に飲食店のメニューと言うのは、原材料を仕入れてから試作し、どれをどのくらい使ったかを原材料の単価から導き出し原価を出します。そこから原価率を何%にすると、利益が出て、かつ召し上がっていただく方にも、それ相応だと思っていただけるかと言う自分と相手とのちょうど良いバランスが取れた値段を決定します。
これがスタンダードな方法だとわかっています。数字がとても好きな僕にとってもそのやり方は実に合理的です。
しかし、このやり方では見逃している点が1つあります。
それは実際に食べられる人の思いはどこにあるのかと言う点です。
上に申し上げました通り、値段を決めるときの(相手とのちょうどいいバランス)と言う一文には【平均的な消費者の意識】が反映されています。
つまり、現場を見ていないということです。
実際には、値段を決めるときに、自分と相手のバランスが取れた値段だと思ったとしても、ご来店いただいたり、お菓子を召し上がったりされた方が、これじゃちょっと……と思うことも少なくありません。
数字で値段を考えて、計算上で値段を決めると現実が置き忘れてしまうと言う結果になるのです。
【こと】来店の意味を知る
現在では日本で(まずいお店)と言う評価を受ける飲食店はほぼありません。
実質賃金は下がっていても、日本の身の回りの豊かさはまだ先進国では上位の方なのではないかと僕は信じています。
そんなおいしいものが溢れている日本、昨今では食べたい(もの)ではなく、行ってみたい(こと)と言う消費動機よりも来店動機の方がお客様の中で重要な気がしています。
この(なぜそこへ行くのか、なぜその店から買うのか)と言うなぜから始まる動機と言うものは数字に置き換えることができません。
(厳密に言うと、置き換えることができるけど、そこまでするほどのお店では、僕の店はありません。)
原価計算と言うのは、基本的にゴールから逆算してスタート位置を決めると言う手法です。
ゴールが決まっているからこそ、その中でどうやって楽しんでいただくかと言う選択肢もおのずと狭まってしまいます。
逆に言うと、選択肢が狭まっている理由はゴールを決めているからと言う点です。
一見して合理的だと思った手法も、対人間関係では決して合理的ではなく、悪手の1つとして例えられるでしょう。
なぜ僕のレストランにお越しいただけるのか。
なぜ僕のお菓子を召し上がっていただけるのか。
レストランにおいては、大阪の中でもあまり行ったことのないであろう平野と言う辺鄙な場所に存在しています。
ここにお店を開いた理由は、現在で主流なSNS戦略…とか言うかっこいい言葉で表すことができない(子供の保育園に近いから)と言う理由です。
なぜ僕のお菓子を召し上がっていただけるのか。
他のお店はどれもクッキー缶や発想の箱がすごくきれいです。
性根が曲がっている僕だから、そんなに豪勢な箱や缶はいらねーだろう。と速攻で批判してしまいそうですが、それも1つの魅力だと思うし、それを魅力として捉えている消費者の方もいることも知っています。
すぐ批判してしまう弱い心は僕の自信のなさの表れだと、自分でも自覚しています。
それなのに、なぜ僕を選んでくれるのか?
それは手前味噌ではありますが、原価計算をしていないで行動に移す理念だと思っています。
一代目は基本、想いを形にする役目
タイトルにありますように、1代目と言う表現を使っていますが、僕はこのお店を1代で終わるつもりですし、次に繋げようともさして思っていません。
しかし、お店を出した以上、必然的に1代目と言う表現になりますので、こう書かせていただきます。
恥ずかしながら、雇われシェフをしていた時よりも、小僧として修行していた時よりも、独立してからの今が1番本を読んでいます。
歴代のフランス料理の歴史を継承して私たちに伝えてくださった諸先輩方、有名飲食チェーンの元社長の自伝
こういう本を独立して、自分が経営者になってからとてもよく読みます。
その中で書いている多くの1代目となっている方々の行動は、多くの場合、後先を考えずにやりたいことをやると言う共通点があると思っています。
初めて創業した人たち、初めて何かを日本に持ち込んだ方々は総じて計算などはせずに、自分の心の中に湧き上がる思いに動かされて行動をしています。
もちろん、本に乗っている方々に比べて失敗している人が何倍も多いと思います。
数字が大好きな僕にとって、働いてきたレストランも無名だし、自分自身も無名なので、どう考えても失敗している方に入る確率が高いと、自分で意識していながらも、
初めて何かを成し遂げた人の気持ちにはとても共感する部分が多いです。
何かを始めた人間は、(電卓を使ってはいけない)のだと思います。
確かに僕にも家庭があります。家族がいます。
ご飯を食べさせてあげたい子供たちもいるし、幸せにしたい妻もいます。
最低限のラインはそれをクリアさせることであって、現在はそれ以上を望んでいない状態でもあります。
現状(妻に食べさせてもらっている)と言う状況ではありませんが、自分がわがままを言って良い状況でもありません。
正直に言うと、そこまで収入が高いと言うわけではないと言うことをオブラートに包んで皆様に伝えています。
いいんです。皆様が同情することではありません。
よくレストランで、(利益は出ているんですか?)と聞かれます。
僕は経営者なので、利益は出さないといけない事は頭ではわかっています。それと同時に僕は職人です。自分がしっかりと突き詰めて究めてきた技術をストレートに召し上がってくれる方々に伝えてわかっていただくにはどうすれば良いかと日々考えています。
恥ずかしながら、先にも申し上げました通り、僕は34歳にして人間ができているとは思っていません。めんどくさい事はめんどくさいし、うざい事はうざいです。
ぶっちゃけて話すと、(お客様の笑顔のために)なんて1度も思ったことがありません。これを読んでる常連の方々大変申し訳ありません。
しかし、ここでお伝えしておきたいのが、僕の役目は何なのかと言う点です。
ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、僕のお店では7月からアルバイトの方を採用しました。
近年、話題のChatGPT4oを取り入れた新しい働き方で、本来ならば雑務から始まる飲食店のアルバイト業務をすっ飛ばして、経営に参加していただく初心者の方を採用しています。右も左のもわからない中で、(僕の店を経営しろ)と言われても不安だと思いますが、基本的に全世界の経験値を蓄えた、生成、AIを隣に置いておくと少しは安心してチャレンジできるだろうと言う試みです。
これからもわかる通り、何かを始めた人は、(2代目の仕事)をしてはいけないということです。
何代目であろうが、経営を知らないと言う事は論外です。
しかし、そこにどのくらいのめり込むかどうかと言うのは、何代目かで変わってくると思います。
私はくしくも1代目です。
1代目と言うのは、歴史が表す通り、自分の思いを自分の考えを世間に伝えていく役割だと思っています。2代目はそのけつを拭き、経営の観点から立て直していくと言う役割だと思っています。
現時点を持って(利益出てるんですか?)と言う質問は僕の問題ではありません。
僕の役割は、利益が出るのか出ないのかと言う瑣末な問題ではなく、これは面白いのか面白くないのかと言う本能の問題だと思っています。
これから先もです、皆様がお目にかかるお菓子は本能に訴えかけるような内容になります。それを作る人間も本能から、そのお菓子たちを選び、その都度おいしさを追求し、改変を重ねます。
タイトル回収になりますが、原価計算を最後にするべき理由と言うのは、
まずはやりたいことが世間に認められるかどうか、やりたいことが皆様に求められているかどうかと言うことを身をもって体験するのが僕の仕事だと思っています。
確かに経営は大切です。アルバイトからスタートする新しいスタッフの方にもしっかりと給料を出さなければいけません。
しかし、僕の店が普通の店と違うと言う点は、アルバイトの人が自分の給料を確保するために店を経営すると言う点です。
逆に言うと、自分が持って帰りたい金額があるのであれば、そのくらい頑張れば自分が持って帰れると言う点です。
正直言って経営がどうだ、会計がどうだ、原価率がどうだと言う尺度で、ものづくりはうまくいきません。
この後にもnoteで書こうと思いますが,
伝統をつないでいくと言うのは、数字ではなく思いだからです。長くなりましたが、頭でっかちの経営では人の信頼は得ることができません。
経営の本質は人が信頼してくれるかどうかに関わってきます。
それを数字だけ見ておけば良いと言うのは論外だと僕は考えています。
ここではっきりと申し上げたいのは、失敗したら失敗しただよね。ということです。
こんなにかっこいいこと言っておきながら、結局失敗も成功も僕の目には見えていません。皆さんのこれを読んだ評価が、ただ僕の未来を左右しているだけで、僕にはそれを管理する能力も知識もありません。
笑ってまうくらい、数字が好きなんかと思えないような人間の結論です。